詐欺の手口がどんどん巧妙化

こんばんは。(#^.^#)
詐欺の手口がどんどん巧妙化しているそうですね。
サイトのURL、メールアドレスのドメイン、電話番号確認など、それぞれに、それなりの確認方法があったのですが、それが通用しない時代になって来ました。
もう、毎日、こんなニュースが何件か流れて来ます。
警察官を装う特殊詐欺、今年1月~2月で1039件・被害額100億円超 実在する警察署の電話番号を着信画面に不正に表示させる手口が急増
SNS型投資詐欺で名古屋市の男性が約7300万円の被害 利益増えるよう見せかける偽サイトに誘導か
「過払い金を返還します」ATM操作を指示され気づいた時には他人の口座に…60歳代女性が35万円だまし取られる
どんどん巧妙化して、URLやメールアドレスも本物と同じになっていたり、電話番号も実在の警察署等の電話番号が使われていたりと、本物か偽物か確認できなくなりつつあるようです。
宅配業者を装った偽メールのお話も、リンクを保存するのを忘れましたが、詐欺被害が多発しているのでと注意喚起の文言まで入っていて、そのリンクをクリックすると、本物のサイトへジャンプしたりと、ライターの方も最後の1歩手前まで本物と思って操作されたようです。
今日は、先日手続きをした郵便局の「e受取チョイス」の届け出が完了しましたというご案内が郵送で届きました(画像)が、佐川さんもヤマトさんもアプリで操作できるようになっているので、アプリから操作すれば、個人情報を入力する必要もなくて安心かな?と…。
受取も、宅配ボックスが選択できるようになっているので、むやみに、玄関ドアを開ける危険性も防げますしね。(;^_^A
私は、原則、宅配ルーム利用で、冷凍品や冷蔵品が届く日以外は直接受取はしません。
宅配業者さんも、不在でも何度も足を運ばれなくても良いので、その方が良いですよね。
以前は、暑い日に重いものを運んで来てくださるとペットボトルのお茶をお渡ししていたりしたのですが、そういう心の機微も失われつつあり、残念ですね。
電話も知らない番号からの着信は、番号調べが終わって、掛かってくる予定がある場合以外、出ないようにしているのですが、重要な用件なら1回だけではなく2回目以降も掛かってくると思うので、1回目は落ち着いて電話番号を調べると良いですよね。
アドレスバーに電話番号を入力して[Enter]するだけで、どこからの電話か分かります。
昨日も朝掛かって来た電話は、気づくのが遅れて、番号を調べようと思っている間に切れてしまって、その後、調べたら「中小企業機構」と分かったので、すぐに電話帳に登録しました。
夕方再度掛かって来たときは、朝の登録ですぐに出ることができて、用件も完了しました。
これも、お問い合わせをしておいたお返事だろうなと推察できたので出たのですが、そうでないと出ないですね。(;^_^A
悲しいことですが、もう、それくらい用心しても良い時代になって来ていますね。
取り敢えず、自分で対策できる部分は、しておかなくっちゃですね。
FP1級より(配当所得と退職所得)
Q1.
ETF(上場投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、上場株式の配当と同様に、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合は配当控除の適用を受けることができる。
A1.(✖)
こういうのって難しいですね。
私は、ETF(イーティーエフ)は購入しているので分かりますが、J-REIT(ジェイリート)は購入していないので、よくわかりませんでした。
- ETFの分配金:総合課税を選択すれば、配当控除の対象となる
- J-REITの分配金:総合課税を選択しても、配当控除の適用は受けられない。
理由は、配当控除は二重課税を減ずる目的で行われるけど、J-REITの分配金は、法人税が免除されるため、二重課税に当たらないからとのことです。
Q2.
内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、原則として、1銘柄につき1回の配当金額が20万円以下であれば、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができる。
A2.(✖)
これは、分かります。
非上場株式の配当には、1銘柄1回の額が年換算で10万円以下なら少額配当に該当し、所得税は申告不要にできるけど、住民税については、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で申告する必要があります。
Q3.
会社員のAさん(55歳)は、勤続25年3カ月で障害者になったことに直接基因して退職することとなり、退職金を受け取った。この場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,320万円となる。
A3.
これは、現在なら〇です。
勤続年数1年未満は1年に切り上げられるので、26年
20年までは40万円/年なので、40×20=800万円
21年目以降は70万円/円なので、70×6=420万円
障がい者になったことに直接起因する退職とあるので、+100万円
800+420+100=1,320万円
たまたま、今日は孫と名古屋の喫茶店で待ち合わせて、待っている間におススメに上がって来た税理士のすがわら先生のYouTubeを拝読していたら、法案が改正されそうで、勤続25年3ヶ月が1箇所なら上の計算のようですが、2ヶ所の通算で仮に13年ずつだったような場合は、それぞれ別に計算され、どちらも40万になってしまうそうですね。
現在は13年ずつでも合算して26年とカウントされる。
労働の流動性を妨げるものだとおっしゃっていたような…。



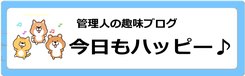



コメントをお書きください